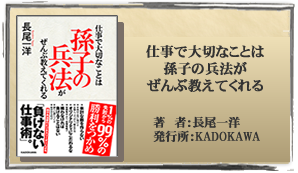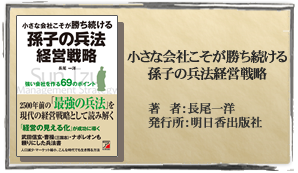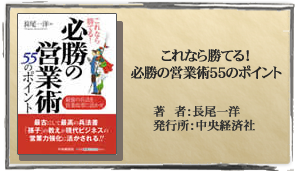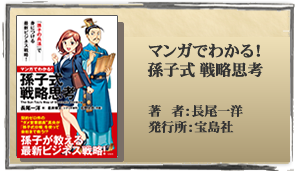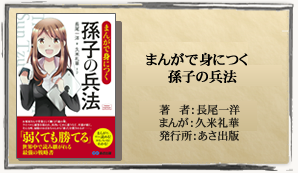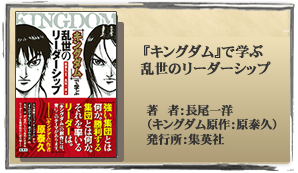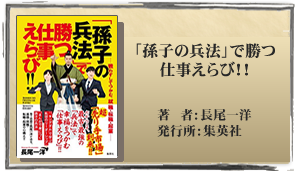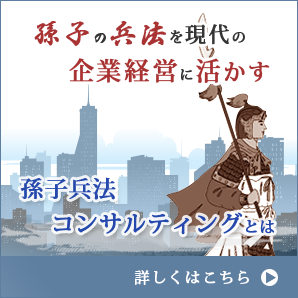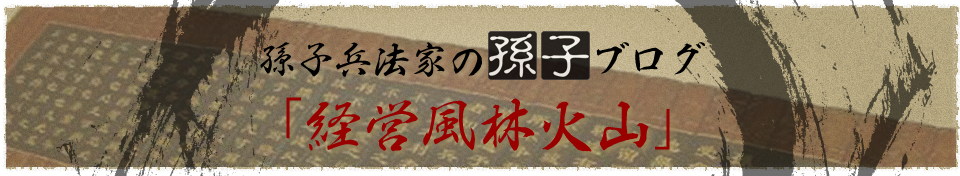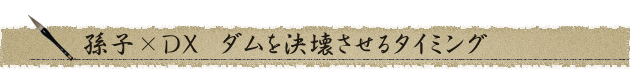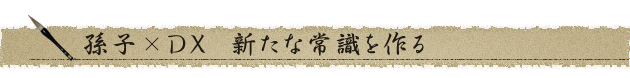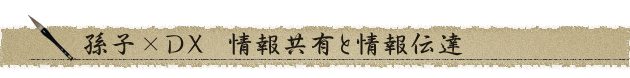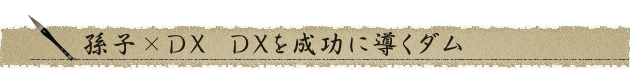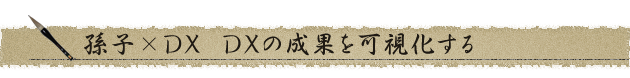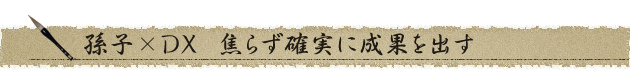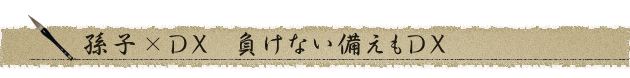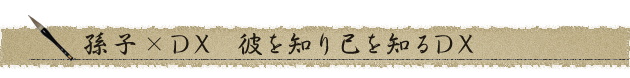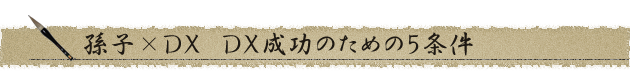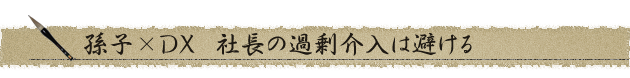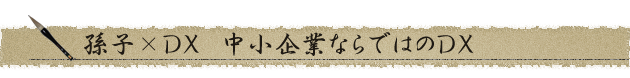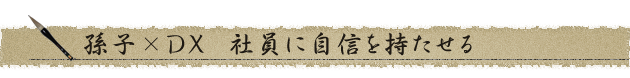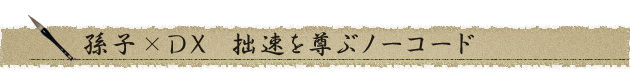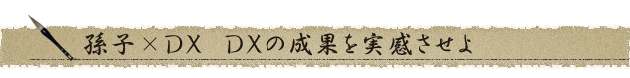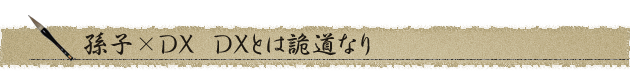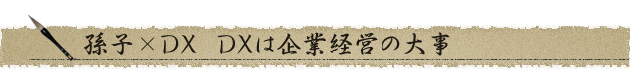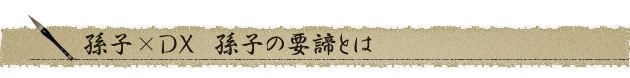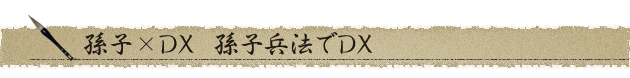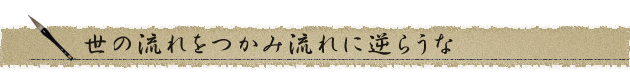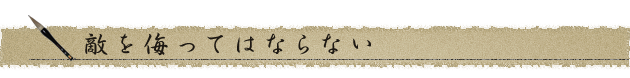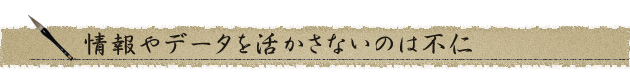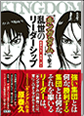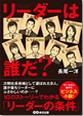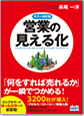- 孫子×DX ダムを決壊させるタイミング
- 孫子×DX 新たな常識を作る
- 孫子×DX 情報共有と情報伝達
- 孫子×DX DXを成功に導くダム
- 孫子×DX DXの成果を可視化する
- 孫子×DX 焦らず確実に成果を出す
- 孫子×DX 負けない備えもDX
- 孫子×DX 彼を知り己を知るDX
- 孫子×DX DX成功のための5条件
- 孫子×DX 社長の過剰介入は避ける
- 孫子×DX 中小企業ならではのDX
- 孫子×DX 戦略的DXとは
- 孫子×DX 社員に自信を持たせる
- 孫子×DX 拙速を尊ぶノーコード
- 孫子×DX DXの成果を実感させよ
- 孫子×DX DXとは詭道なり
- 孫子×DX DXは企業経営の大事
- 孫子×DX 孫子の要諦とは
- 孫子×DX 孫子兵法でDX
![孫子の兵法[最新記事一覧]](img/menu1.png)
- 孫子×DX ダムを決壊させるタイミング
- 孫子×DX 新たな常識を作る
- 孫子×DX 情報共有と情報伝達
- 孫子×DX DXを成功に導くダム
- 孫子×DX DXの成果を可視化する
- 孫子×DX 焦らず確実に成果を出す
- 孫子×DX 負けない備えもDX
- 孫子×DX 彼を知り己を知るDX
- 孫子×DX DX成功のための5条件
- 孫子×DX 社長の過剰介入は避ける
- 孫子×DX 中小企業ならではのDX
- 孫子×DX 戦略的DXとは
- 孫子×DX 社員に自信を持たせる
- 孫子×DX 拙速を尊ぶノーコード
- 孫子×DX DXの成果を実感させよ
- 孫子×DX DXとは詭道なり
- 孫子×DX DXは企業経営の大事
- 孫子×DX 孫子の要諦とは
- 孫子×DX 孫子兵法でDX
- 世の流れをつかみ流れに逆らうな
- 敵を侮ってはならない
- 情報やデータを活かさないのは不仁
- 電帳法対応でも孫子は水に象る
- 営業風林火山陰雷
- 「孫子兵法家」商標登録
- スプリンクラーで水攻めせよ
- 緊急事態は巧久ではいけない
- 経営は企業の大事なり
- コンタクトレス・アプローチと営業の見える化
- そして、重版出来!!
- セールス・営業分野で1位ゲット
- 勢いは険しくタイミングは短く集中
- 千里を一気に飛ぶコンタクトレス・アプローチ
- コロナウイルスとの戦い
- ESGにも孫子の兵法を活かす
- SDGsにも孫子の兵法を活かす
- ONE TEAMも孫子の教え?
- 孫子であきない話
- 営業マンは売り子ではなく間諜である
- 定石を知っていてこそ応用も利く
- ラジオで孫子のプロパガンダ
- 見るだけで孫子の兵法が分かる?
- 属人性を排除せよ
- GAFAと孫子兵法
- 孫子兵法でパワハラを考える
- W杯ロシア大会日本代表
- 重版決定!!感謝!
- AIも孫子兵法?
- 宮原知子と孫子兵法
- 千里なるも戦うべし
- 2010年~2017年
![孫子の兵法[年別アーカイブ]](img/menu2.png)